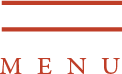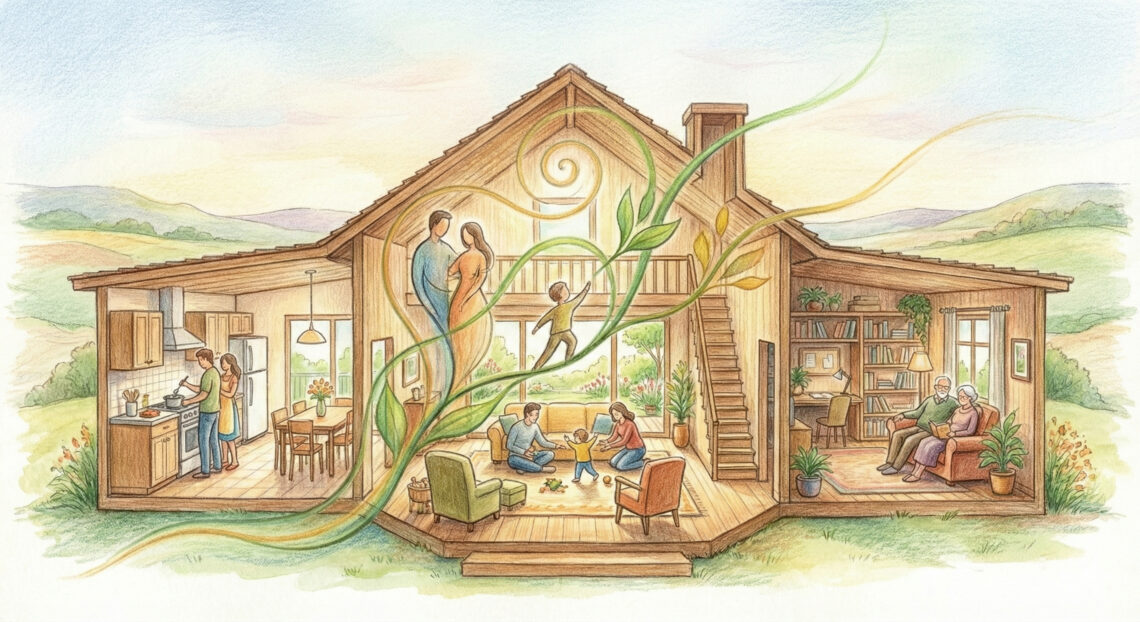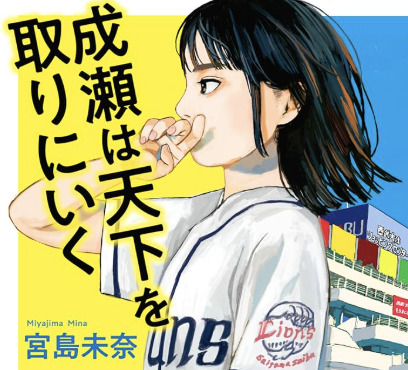2025.7.27 日
そうめんとひやむぎの違いを知っていますか?(太さらしいです)
みなさんこんにちは。
広報部の佐野です!
夏ですね!そうめん食べてますか?

自分はこれまでそうめんというものにあまり魅力を感じていなかったのですが、今年の夏、急に「そうめんが食べたい!!」と感じるようになったのです。喉が求めてきたんです。
あのツルッとした感覚、たまらないですよね!
幼い頃に食べたあの感覚を今更思い出したのでしょう。
自分はうどんが好きなので、素材として変わらないそうめんに惹かれ合うのは必然なのかもしれませんが、素材が同じならばなぜ分類が分けられているのでしょうか??
というところに疑問を抱いたところで、今回はそんなそうめんの話です。
よかったら最後まで読んでくださいね〜!
麺の分類
現在ではJAS(日本農林規格)によって
そうめん:1.3mm未満
ひやむぎ:1.3〜1.7mm未満
うどん:1.7mm以上
という太さ基準による分類が明確に定められています。(乾麺に限る)
つまりうどんと同じ製法でも、1.3mm未満であればそれはそうめんになるらしいです。
また、甘味成分であるデンプンは麺が細いほど茹でた際に流れ出てしまうため、うどん→ひやむぎ→そうめんの順に甘みが強いとのことです!
麺自体にも味を求める自分が、これまでそうめんに魅力を感じなかった理由はここにあるのかもしれません。
ひやむぎの存在
そうめんとうどんの間にしれっと現れたひやむぎという存在。
彼はなぜちょうど、そうめんとうどんの間にいるのでしょうか。
太めのそうめん、細めのうどん、そんな表現でもいいのでは?
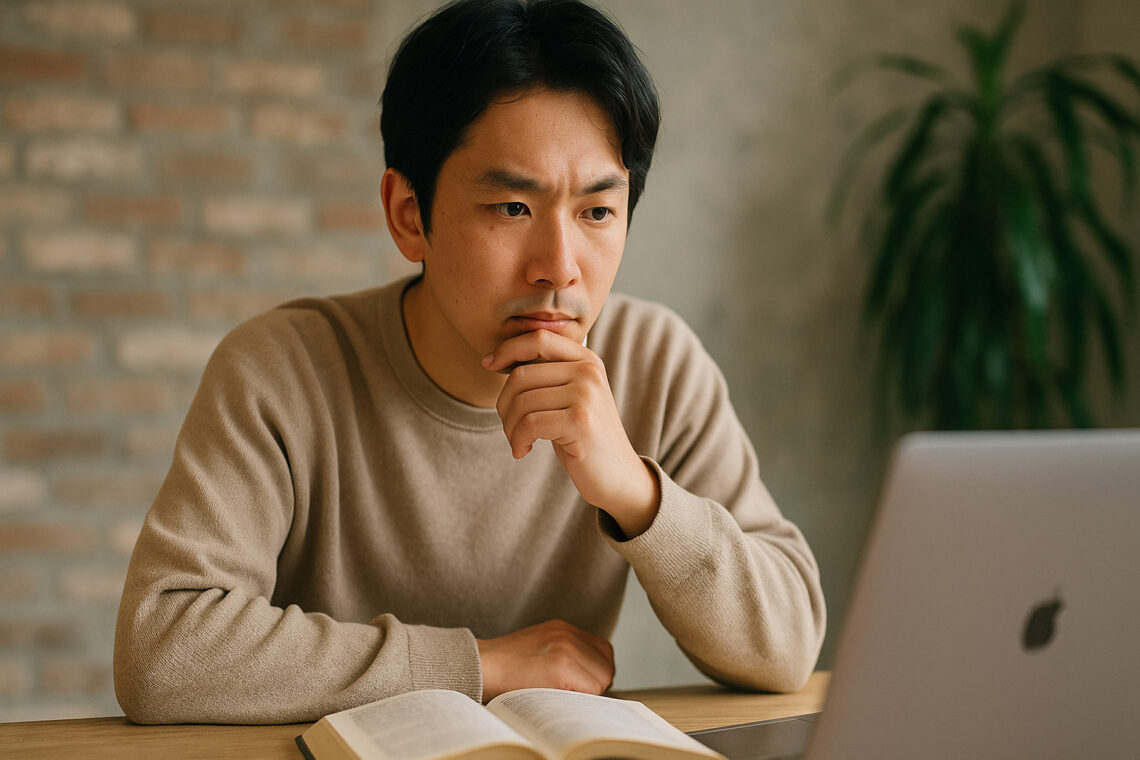
気になって調べてみたらこれがなかなか奥深くて面白かったので少しご紹介しますね。
⸻
1. 奈良〜平安時代|そうめんのルーツはお菓子!?
そうめんの祖先とされているのは「索餅(さくべい)」という中国から伝わったお菓子のような食べ物。
縄のようにねじった小麦麺で、奈良時代の宮中行事などでも登場していたそうです。
ちなみに、七夕にそうめんを食べる風習のルーツもここにあるんだとか。
⸻
2. 鎌倉〜室町時代|手延べそうめんの誕生
現在の「そうめん」のスタイルが確立したのはこの頃。
奈良県・三輪の僧侶たちが中国の製法をベースに、油を塗って細く引き延ばす技術を編み出したとされています。
あの喉ごしは700年くらい前に完成されていたんです。
⸻
3. 江戸時代|ひやむぎ、名乗りを上げる
江戸時代に入ると、より手軽に作れる「切り出し型」の細麺が登場。これが「冷麦(ひやむぎ)」です。
そうめんに比べて安価で作りやすく、庶民の間にスルスルと広がっていったそうです。
⸻
4. 明治〜昭和|冷たい麺文化の一般化
流通の発展とともに、冷やして食べる文化が全国に普及。
ひやむぎやそうめんは、夏の定番として庶民の食卓に定着していきました。
流しそうめんなんて文化もこの頃に盛り上がってきたみたいです。
⸻
5. 現代|名前の決め手は「太さ」だけ
そして時代は現代。
機械製麺が主流になったことで製法の違いは少しずつ曖昧に。
そのため現在では「そうめん/ひやむぎ/うどん」は乾麺に限っては太さだけで分類されることになりました。
⸻
ということで太さの基準は機械化の影響で規格化されたに過ぎないということです。
もともとは庶民向けの安価なそうめんの代役として登場したのがひやむぎの始まりだったのですね。

ふと気になったことを調べてみるのは新たな発見があって面白いですね。
今日はそんなひやむぎを買って帰りたいと思います。それではまたお会いましょう!
暮らしを彩るHARMONYマガジン
家づくりの疑問やライフスタイル、お金や土地のことから耐震や断熱の性能のことまで家づくりに役立つ情報を発信中!
家づくりをお考えの方は覗いてみてください👀
上質な暮らしを体験できるCreative House
松阪ハウジングセンター内にあるモデルハウス【Villa Vision】
自信をもってご提案できる建築力とデザイン、自然素材を使ったあたたかみのある空間が魅力のモデルハウスです。新しい暮らしのイメージをぜひご体験ください。
個別無料相談会開催中
家づくりに関する様々なご相談をお受けしています。土地探しや間取り、資金計画など住宅のプロがお悩みを解決いたします。【津オフィス】【鈴鹿オフィス】【松阪ショールーム】【伊勢オフィス】の4つのオフィスでお待ちしております。

佐野 紅葉
KOYO SANO